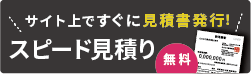キャッチコピーの基礎から応用までの考え方とコツを紹介!

キャッチコピーとは、商品やサービスの販売促進、企業ブランディングを目的として使われる短いフレーズのことです。広告やパンフレット、商品パッケージやPOPはもちろん、ウェブサイトやSNS等で、私たちは日常的にたくさんのキャッチコピーを目にしています。
この記事では、キャッチコピーとは何か、なぜ必要なのかといった概要から、作成する際の考え方やコツまでを分かりやすくまとめています。キャッチコピーを考える際のヒントとしてお役立てください。
キャッチコピーとは
キャッチコピーのアイデアを出す前に、キャッチコピーとはどういったものを指すのか、なぜキャッチコピーが必要なのかといった基本的な情報をご紹介します。
キャッチコピーには2種類ある
キャッチコピーとは、商品やサービスの販売促進、企業ブランディングを行う際に、ターゲットとなる顧客の興味や関心を集めることを目的として付ける宣伝文句です。キャッチコピーには、イメージキャッチコピーとセールスキャッチコピーの2種類があります。
イメージキャッチコピーは、顧客の印象に残るために作られるものです。企業理念や文化、価値観などをアピールして他社との差別化を図り、企業イメージを高めます。
セールスキャッチコピーは、商品やサービスの購入を促すために作られるものです。商品やサービスの魅力を直接的にアピールし、購買意欲を刺激します。
なぜキャッチコピーが必要なのか
キャッチコピーを利用すると、商品・サービスや企業名が記憶に残り、認知が高まります。その結果、たくさんの商品が並んでいる店頭であっても該当商品へ意識が向き、認知が低い状態と比べて購入されやすくなります。また、キャッチコピーがブランディングの役割を果たし、企業イメージの定着につながるという点もキャッチコピーの必要性の一つです。
キャッチコピーの考え方とコツ
キャッチコピーには、基本的な考え方とコツがあります。見通しを持たないまま作り始めるのではなく、まずはキャッチコピーの基礎を押さえておきましょう。
ターゲット層と目的を明確にする
キャッチコピーを作成する時は、ターゲット層とその目的を明確にすることが大切です。つまり、キャッチコピーを届けたいのはどんな顧客か、キャッチコピーを受け取った顧客にどうなって欲しいのかを考えていきます。
ターゲットが個人の場合は、年齢層や性別、職業や居住地、家族構成や趣味といった属性を絞ります。ターゲットが企業の場合は、業種や事業内容、企業規模や従業員数などを定めていきます。ターゲット層を明確にすることで、「商品を買って欲しい」「企業イメージをアップしたい」といった目的を明確にすることができるのです。
ターゲットの悩みと自社の強みを組み合わせる
続いて、先ほど定めたターゲットが持っている悩みと自社の強みを組み合わせます。必要なのは、自社の強みがターゲットの悩みを解決するためにぴったりだと示すことです。
例えば、野菜不足に悩んでいる社会人に野菜ジュースを買って欲しいのであれば、「通勤中に飲むだけでサラダ一皿分」といったワードはいかがでしょうか。あるいは、ペーパーレス化の推進に限界を感じている企業の担当者に書類電子化サービスをアピールしたいのであれば、「コピー用紙使用量前年比7割減」といった言葉が刺さるかもしれません。
キャッチコピーを作るときのテクニック
キャッチコピーのターゲット層と目的、ターゲットの悩みを解決できる自社の強みを定めたら、いよいよキャッチコピーを作るプロセスに入ります。効果的なキャッチコピーを作るためのテクニックは、以下の3つです。
テンポ感のいいものにする
耳に残るキャッチコピー、声に出して言いたくなるキャッチコピーは、顧客の印象に残りやすいと言われています。キャッチコピー全体の文字数、口ずさんだ時の語呂の良さ、テンポ感などを意識しましょう。
例えば、フルーツマリネのキャッチコピーとして「くだもの、すのもの、にんきもの」などは韻を踏んでいてテンポも良いのではないでしょうか。
ターゲットの感情に訴える
ターゲットの立場になって、その悩みを解消するような内容や需要を満たすような内容をキャッチコピーに盛り込むのも有効です。信頼性を担保するために、社会的に信頼や影響力を持っている人物や団体を利用する方法もあります。そういったテクニックで作られたキャッチコピーによって、ターゲットの感情はポジティブにもネガティブにも刺激されます。そして「私も同じように悩みを解決できるかもしれない」、もしくは「私もそうしないと置いていかれるかもしれない」といった共感や不安を呼び、購買行為につながるのです。
例えば、「気になる夏の臭いにさよならできるサプリメント」、「株式会社〇〇のトップ営業が教える営業トークA to Z」といったキャッチコピーがこのテクニックに該当します。
具体的な数字を使う
キャッチコピーに具体的な数字を使うことで、商品やサービスから得られるメリットをイメージしやすくなります。よくあるのは、「◯秒に1個売れている」や「総売上個数〇〇個突破」といった売上実績です。また、何らかの効果が得られる商品やサービスの場合、「◯日でできる」や「◯kg痩せる」といった数値の使い方も効果的です。それだけではなく、店舗数や来店者数、商品の重さや大きさ、無料でサービスを試せる期間など、キャッチコピーに使える数字には様々なものがあります。
どうしても思いつかない場合
ここまでの内容を踏まえたうえで、どうしても思いつかない場合のヒントをお伝えします。困った時は参考にしてください。
顧客アンケートや口コミなどを参考にする
顧客アンケートや口コミは、キャッチコピーのアイデアの宝庫です。顧客が実際に商品やサービスを使ってみた感想、魅力に感じた点、不満に感じた点など、たくさんの情報を拾い上げることができます。最終的に商品・サービスを購入し、使うのは顧客です。顧客の反応を分析することで、気付いていなかった顧客目線の自社の強みを発見できることもあります。
ターゲットの行動をイメージする
商品・サービスを使うターゲット層と同じ行動をとることで、キャッチコピーのアイデアが湧くこともあります。何を考えて商品を手に取るのか、サービスのどんな部分に期待しているのか、物理的に顧客目線に立つことで分かることがあるからです。商品やサービスによっては、同じ行動をとるのが難しいこともあります。その場合は、カスタマージャーニーなどを作成し、ターゲットの行動をイメージしてみてください。
キーワードを見つけてみる
商品やサービス、ブランドのウェブサイトが既にある場合は、顧客がどんなキーワードで検索してウェブサイトにたどり着いているのかを確認してみましょう。検索エンジンに入力されるキーワードには、顧客の悩みやニーズが端的に現れるからです。自社製品に限らず、検索されることの多いキーワードはキャッチコピーのヒントになります。
また、社内で使いがちなフレーズや共通認識となっている言葉をピックアップしてみるのもおすすめです。
まとめ
キャッチコピーの概要から、作成する際の考え方・コツ、テクニックやヒントをご紹介しました。
普段は何気なく触れているキャッチコピーですが、いざ自身が作る立場に立つと奥が深く難しい世界であることが分かります。キャッチコピーと聞いてすぐに頭に浮かぶフレーズがあれば、それはあなたという顧客に届いた効果的なキャッチコピーだったということです。そのキャッチコピーにどんなテクニックが使われているのか、考えてみるのも面白いでしょう。この記事で解説したポイントを押さえて、魅力的なキャッチコピーを作ってみてください。
キャッチコピーを考える際は併せて色味も意識してみてはいかがでしょうか。目立つ色でより顧客を引き付けることができるかもしれません。目立つ色の組み合わせについてこちらのコラムでご紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。